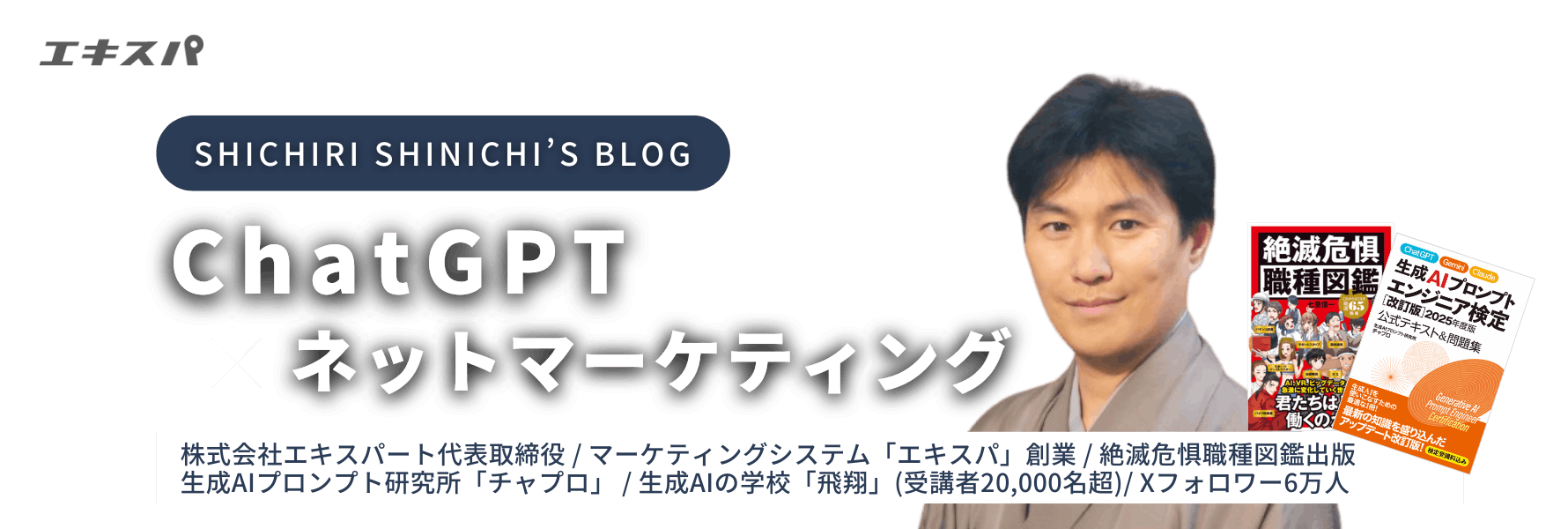実作業への生成AI活用(3-1)
2025/08/06

七里です。
今回は、
実作業への生成AIの活用方法について
全部で3回に分けて
お届けしていきたいと思います。
生成AIとは何か?
まず最初なんですけど、
生成AIの活用って
再現可能なデジタル成果物の
製造システムの構築ということなんです。
要は、デジタルデータを何度でも簡単に、
工場の生産ラインのように作っていく
ということです。
私の場合、
いま代表取締役社長をしていますが、
うちの会社にはデザイナー、プログラマー、
ライターなど、デジタルデータを作れる
スキルのあるスタッフがいます。
その人たちに指示を出せば、彼らが考えて
デジタル成果物を作ってきてくれます。
正直わたしは、この”デジタルデータを作る”
という部分で言ったらそこまで大きな差は
出ないんですが、
うちのデザイナー、プログラマー、
ライターたちは、作業が非常に
楽になっていますし、
私と同じようなことができるように
なってきているわけなんです。
作業の標準化と能力差の解消
それができるとどうなるか。
作業の標準化・自動化が可能になります。
出来上がったプロンプトやAIの仕組みが
あれば、誰でも同じようなクオリティを
出すことができます。
例えるならば、
テープ起こしや文字起こしです。
昔はテープで聞きながら
人力で文字起こしをしていました。
この作業は人によって
作業品質に差が出てきてしまいますよね。
でも今は、音声データを入力するだけで
音声データすべてテキストデータ化
してくれます。
こういうことによって、
能力差がほぼ無くなったんです。
テンプレート化で成果物を量産できる
さらに、
プロンプトやAIシステムが出来上がると、
初期入力値を変更するだけで
成果物が作れる「型」
つまりテンプレートができるんです。
たとえば「マンガを作ってください」
という指示をしたとします。
マンガの題名、ストーリー、キャラクター名を
初期入力として入れるだけで、
10ページのマンガがポンッと生成されます。
開業するマンガを作りたい場合、
初期入力値を「ラーメン屋」にすれば
ラーメン屋の開業マンガができるし、
初期入力値を「美容室」にすれば
美容室の開業マンガが出来上がるわけです。
つまり、初期入力を変えるだけで
成果物が簡単に量産できるようになる。
こういうのも
作業の標準化・自動化に使えます。
専門知識がなくてもOKな時代
専門知識がなくても高品質な
デジタル成果物を作れるようになります。
でも実際、マンガを作るためには
とてつもない修行が必要なんです。
私もマンガLPというセミナーを開いたとき
週1回マンガ学校に教わりに行きました。
とんでもなく難しいですからね。
本気でマンガ家になろうと思ったら
10年は必要なレベルです。
でも私は今、AIを活用して
マンガを作る「型」を持っています。
この型を使えば、
あなたでもマンガ家になれるんです。
1万時間とか2万時間の修行はいらないです。
AIの基礎知識があれば
あとはこの型の使い方を覚えるだけ。
そうすれば、誰でもマンガ家になれます。
80点のクオリティを誰でも再現可能に
もちろん、
宮崎駿さんや手塚治虫さんのように
120点のものは作れません。
ただし、たかだか数時間ちょっと使い方を
勉強しただけで80点くらいのものを
誰でも作れるようになる。
というのがすごいことなんです。
一定の成果物の品質を保つこともできるし、
初期入力値を変更するだけ。
これが作業の標準化・自動化として
AIがもたらすものです。
まとめと次回予告
今回は、
生成AIを活用すれば専門知識がなくても
誰でも高品質な成果物を量産できる
という話でした。
テンプレート化された仕組みを使えば、
作業が劇的に効率化され、
結果も安定して出せるようになります。
次回はさらに一歩進めて、
・AIでどれだけ時間とコストを
減らせるのか
・人との役割分担でどこまで成果を
高められるのか
を具体的にお伝えします。
学びや気づきがあればぜひコメントで
教えてください。
七里
今回は、
実作業への生成AIの活用方法について
全部で3回に分けて
お届けしていきたいと思います。
生成AIとは何か?
まず最初なんですけど、
生成AIの活用って
再現可能なデジタル成果物の
製造システムの構築ということなんです。
要は、デジタルデータを何度でも簡単に、
工場の生産ラインのように作っていく
ということです。
私の場合、
いま代表取締役社長をしていますが、
うちの会社にはデザイナー、プログラマー、
ライターなど、デジタルデータを作れる
スキルのあるスタッフがいます。
その人たちに指示を出せば、彼らが考えて
デジタル成果物を作ってきてくれます。
正直わたしは、この”デジタルデータを作る”
という部分で言ったらそこまで大きな差は
出ないんですが、
うちのデザイナー、プログラマー、
ライターたちは、作業が非常に
楽になっていますし、
私と同じようなことができるように
なってきているわけなんです。
作業の標準化と能力差の解消
それができるとどうなるか。
作業の標準化・自動化が可能になります。
出来上がったプロンプトやAIの仕組みが
あれば、誰でも同じようなクオリティを
出すことができます。
例えるならば、
テープ起こしや文字起こしです。
昔はテープで聞きながら
人力で文字起こしをしていました。
この作業は人によって
作業品質に差が出てきてしまいますよね。
でも今は、音声データを入力するだけで
音声データすべてテキストデータ化
してくれます。
こういうことによって、
能力差がほぼ無くなったんです。
テンプレート化で成果物を量産できる
さらに、
プロンプトやAIシステムが出来上がると、
初期入力値を変更するだけで
成果物が作れる「型」
つまりテンプレートができるんです。
たとえば「マンガを作ってください」
という指示をしたとします。
マンガの題名、ストーリー、キャラクター名を
初期入力として入れるだけで、
10ページのマンガがポンッと生成されます。
開業するマンガを作りたい場合、
初期入力値を「ラーメン屋」にすれば
ラーメン屋の開業マンガができるし、
初期入力値を「美容室」にすれば
美容室の開業マンガが出来上がるわけです。
つまり、初期入力を変えるだけで
成果物が簡単に量産できるようになる。
こういうのも
作業の標準化・自動化に使えます。
専門知識がなくてもOKな時代
専門知識がなくても高品質な
デジタル成果物を作れるようになります。
でも実際、マンガを作るためには
とてつもない修行が必要なんです。
私もマンガLPというセミナーを開いたとき
週1回マンガ学校に教わりに行きました。
とんでもなく難しいですからね。
本気でマンガ家になろうと思ったら
10年は必要なレベルです。
でも私は今、AIを活用して
マンガを作る「型」を持っています。
この型を使えば、
あなたでもマンガ家になれるんです。
1万時間とか2万時間の修行はいらないです。
AIの基礎知識があれば
あとはこの型の使い方を覚えるだけ。
そうすれば、誰でもマンガ家になれます。
80点のクオリティを誰でも再現可能に
もちろん、
宮崎駿さんや手塚治虫さんのように
120点のものは作れません。
ただし、たかだか数時間ちょっと使い方を
勉強しただけで80点くらいのものを
誰でも作れるようになる。
というのがすごいことなんです。
一定の成果物の品質を保つこともできるし、
初期入力値を変更するだけ。
これが作業の標準化・自動化として
AIがもたらすものです。
まとめと次回予告
今回は、
生成AIを活用すれば専門知識がなくても
誰でも高品質な成果物を量産できる
という話でした。
テンプレート化された仕組みを使えば、
作業が劇的に効率化され、
結果も安定して出せるようになります。
次回はさらに一歩進めて、
・AIでどれだけ時間とコストを
減らせるのか
・人との役割分担でどこまで成果を
高められるのか
を具体的にお伝えします。
学びや気づきがあればぜひコメントで
教えてください。
七里
コメントはこちらから